20250504日曜午後礼拝
聖書:マルコ10:13−16
題目:子供に習おう
説教者:高曜翰 副牧師
“イエスにさわっていただくために、人々が幼な子らをみもとに連れてきた。ところが、弟子たちは彼らをたしなめた。それを見てイエスは憤り、彼らに言われた、「幼な子らをわたしの所に来るままにしておきなさい。止めてはならない。神の国はこのような者の国である。 よく聞いておくがよい。だれでも幼な子のように神の国を受けいれる者でなければ、そこにはいることは決してできない」。 そして彼らを抱き、手をその上において祝福された。”
マルコによる福音書 10:13-16 口語訳
1。子供の日
第一次世界大戦後、敗戦国のドイツやオーストリアでは、多くの子供が餓死寸前の状態でした。それを見かねたイギリス人女性のエグランティン・ジェップ(1876−1928)は「セーブ・ザ・チルドレン」という子供を支援する団体を設立しました。当時、敵国に対する支援などあり得ないという風潮でしたが、「子供に国境はない。全ての子供に生きる権利がある」と言って、支援を行いました。1924年には「子供の権利宣言」を国際連盟に提出し、1959年にも国際連合で採択されました。1989年には「子どもの権利条約」が制定され、とうとう法的拘束力を持つようになりました。この条約では子供の生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利が保障されます。日本でもこの条約が1994年批准され、1995年には「児童虐待防止法」が日本国内で施行されました。
世界的に子供の人権が認められるようになってきてはいますが、まだまだ子供の人権を無視する児童虐待は多く残っています。2024年のユニセフの調査では、5歳未満の子供の60%は日常的に虐待を受けていると言われています。人類は長い歴史の中で、子供に価値を置きませんでした。しかし、聖書では子供に価値を置くように教えています。今日の聖句を通して、私たちが子供を見る時の視線が変わることを期待します。
2。イエスの怒り
イエスがガリラヤを離れ、エルサレムに入る直前のお話です。イエスはいつものように人々から質問攻めに会っていました。そんな中で、ある人々が子供たちをイエスの前に連れてきました。イエスに触ってもらい、祝福を得るためです。ユダヤには、子供たちを長老たちの所に連れて行き、祝福してもらう習慣がありました。有名人のイエスにしてもらえれば効果が高いと考えたのではないでしょうか。しかし、弟子たちが、子供たちを連れてくる人々を叱りました。ここでは、「エピティマオ」という、悪霊を叱りつけて追い出す時と同じ単語を使用しています。激しく叱っている事がわかります。イエスの仕事が子供に邪魔されてはいけないという考えがあったのでしょう。当時は乳幼児の死亡率が高かった事から、子供に対する期待値は全体的に低かったと考えられます。子供の人格は尊重されず、「人になる前の存在」程度に考えられていました。パリサイ人たちも、律法を学ぶことができない子供は、神の国に入れない哀れな存在だという認識でした。時代背景を鑑みれば、弟子たちの行動は何ら不思議なことではありませんでした。
しかし、イエスは弟子たちに対して憤りました。「アガラテオ」という単語が使われていますが、非常に不愉快な状態を表しています。ナルドの香油を割ったマリアに対して憤った弟子たちに使われたのと同じ単語です。イエスは、弟子たちが子供たちを無視する態度に対して、明らかに不満を抱きました。イエスは「子供が来るのを止めてはならない。神の国はこのような者の国である」と言いました。律法を学んで知識がある大人ではなく、神の国は子供たちにこそ相応しいと言っているのです。イエスは「よく聞きなさい」と言いました。つまり、「あなたたちの一般常識と違うことをこれから言います」ということです。ユダヤ社会の伝統的な考え方を否定し、神の国の新常識を話そうとしているのです。
それは、神の国に入る条件が、子供のようになることだということです。文脈を見ると、今日の聖句の前に、パリサイ人が律法をかいくぐって離婚できる方法をイエスに聞いています。また、今日の聖句の後に、律法を遵守している青年が神の国に入る方法を聞いています。どちらも、イエスを罠にはめようと知恵を振り絞っているのがわかります。
しかし、神の国にふさわしいのは、これらの大人たちと真逆の子供達であるとイエスは教えています。知的な者が正しいというのは、ギリシャ的であり、この世の考え方です。しかし、神の国では、知識ではなく、単純で素直な心が正しいのです。頼ることしかできず、自分で解決できない無知や弱さがむしろ喜ばれるのです。そして、イエスは子供達を抱いて、祝福しました。触ってもらったら祝福がある、という迷信的な信仰を認めたわけではありません。その単純で素直な心を認めたのです。自分ではなく、神様に頼る心を神様は喜ばれます。
3。子供に学ぶ事
まず、知識の多さではなく、心の単純さが大事です。
“だから、すべての汚れや、はなはだしい悪を捨て去って、心に植えつけられている御言を、すなおに受け入れなさい。御言には、あなたがたのたましいを救う力がある。”
ヤコブの手紙 1:21 口語訳
汚れや悪を捨てて、素直に御言葉を受け入れるように教えています。言い換えれば、汚れや悪が、素直さを奪い、植え付けられている御言葉を受け入れなくしているのです。しかし、素直さを奪うのは、知識も同じです。パウロは愛のない知識は無に等しいと言っています(1コリント13:2)。賢い人ほど上手い言い訳が思いつき、素直になれません。知識が多い人ほどその心も複雑です。その知識のせいで、御言葉通りに生きる機会を失っているのです。ある未信者の方は「聖書を受け入れたら、今までの自分が積み重ねたモノが壊れてしまう」と言いました。多く積み重ねた人ほど、過去を捨てる事ができないのです。その過去のせいで自分の命が失われるとしてもです。逆に、単純な人ほど、簡単に過去を捨てて、神様に合わせる事ができます。「私の父なる神様はすごい!神様についていこう!」これでいいのです。世の中では単純な人がバカを見ると言いますが、神の国では単純な人が恵まれています。
次に、強くなろうとするのではなく、弱さを受け入れる事が大事です。
“ところが、主が言われた、「わたしの恵みはあなたに対して十分である。わたしの力は弱いところに完全にあらわれる」。それだから、キリストの力がわたしに宿るように、むしろ、喜んで自分の弱さを誇ろう。”
コリント人への第二の手紙 12:9 口語訳
弱いから神様の力が現れるのだと、パウロは喜んでいます。この世では、強い者が神様に愛されていると考えます。しかし、神様が働くと、私たちの強さはどんぐりの背比べであり、関係がありません。むしろ、強者は自分を誇るので、神様が力を表わしにくくなります。アメリカのジョン・パイパー牧師は、弱さを受け入れると良いことがあると教えています。自己中心的な誇りを防ぎ、神様に頼るしかなくなります。人間の限界を知り、神様の力が大きく現れます。弱さによる経験が、他者への理解と共感を深めます。神様が用いやすい人になるのです。信仰とは、子供のように神様に頼ることです。この世では誰かに頼ることが悪いことのように言います。しかし、神の国では、神様に頼らない事が悪いことになります。つまり、強くなろうとするのではなく、弱さを認めることが神の国では大切なのです。
素直に神様に頼る事を、子供の姿を見るたびに思い出しましょう。
“あなたがたは、これらの小さい者のひとりをも軽んじないように、気をつけなさい。あなたがたに言うが、彼らの御使たちは天にあって、天にいますわたしの父のみ顔をいつも仰いでいるのである。”
マタイによる福音書 18:10 口語訳
イエス様は、子供を見て、見下す心を持たないよう警告しています。子供達についている天使は、天にいる父なる神様の顔をいつも見ていると言っています。つまり、子供たちは特に神様と深く繋がっており、子供達への悪い心は、すぐに神様にバレるという意味です。昔ながらの、子供に価値はないという考えは誤りです。確かに、子供には、知識も経験も、力も足りません。しかしそれが悪いわけではないのです。当然、子供を甘やかすのではなく、正しく導くのが大人の役割ですが、子供を通して大人も学ぶことができるのです。神の国に近い存在は私たち大人ではなく、子供であることを認めてください。
4。まとめ
子供は素直に神様に頼ります。子供は自分の弱さを知っているから神様に頼ります。子供のような心を持った人こそが、神の国にふさわしい存在です。この事実を。子供を見る度に思い出すことができれば幸いです。


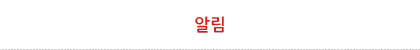
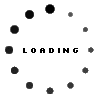
댓글0개