20251019日曜日本語礼拝
聖書:マタイ28:18−20
題目:教会は弟子を作る台所
賛美:9、499、498
“イエスは彼らに近づいてきて言われた、「わたしは、天においても地においても、いっさいの権威を授けられた。 それゆえに、あなたがたは行って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって、彼らにバプテスマを施し、 あなたがたに命じておいたいっさいのことを守るように教えよ。見よ、わたしは世の終りまで、いつもあなたがたと共にいるのである」。”
マタイによる福音書 28:18-20 口語訳
1。宣教と料理
台所での料理と教会での宣教は似ているように思います。料理の手順は「食材を用意する」「調理する」「盛り付ける」「食べてもらう」とたくさんありますが、実質的な目的は「食べてもらう」ことにあります。他の3つの工程は「食べてもらう」ための手順であり、どれだけ3つの手順を素晴らしくしても「食べてもらう」ことができなければ意味がなくなってしまいます。
今日の本文を見ると、宣教の手順が書かれています。「行く」「弟子を作る」「洗礼を施す」「教える」とたくさんあります。しかし、実質的な目的はひとつです。それは、「弟子を作る」ことです。ギリシャ語を見ると、「行く」「洗礼を施す」「教える」は分詞であり、命令動詞は「弟子を作る」の一つだからです。他の3つの手順は「弟子を作る」ための方法であり、どれだけ3つの手順を素晴らしくしても「弟子を作る」ことができなければ意味がなくなってしまいます。
本日は、教会の目的の一つである宣教が弟子を作ることであり、そのための3つの手順がどのようなものかを見ていきたいと思います。ただし、ひとつひとつの手順で負担に思わないでください。3つの手順はあくまで、より良い「弟子作り」のためのヒントなのですから。
2。出て行く
まず「行く」という工程ですが、ギリシャ語で「ポルーオ」という単語が使われています。これは、避難や脱出といった受動的な意味はなく、目的を持って出ていくという能動的な意味があります。弟子作りには、自ら出ていくことが大切なのです。教会は入って終わりではなく、出ていくための始まりの場所です。台所は食材を保管して終わる場所ではなく、食材を出して調理する場所です。宣教での「行く」は、料理での「食材を用意する」に当たります。私たちが受けた恵みは、教会で保存するのではなく、誰かに与えるために貯蔵庫から取り出す必要があるのです。教会はめぐみの貯蔵庫ではなくパイプのような役割があるのです。
そして恵みを与える対象は全ての人々です。イエスは、異邦人やサマリヤ人に行かず、イスラエル人に行きなさい(マタイ10:5−6)、と弟子たちに言いました。しかし実際は、サマリヤやデカポリスにも行っております。これはイエスの言動がコロコロ変わっているのではなく、これは神様の戦略のためです。戦略的には私たちが対象を絞りますが、神様の望みは差別することなく「全ての人々」に対して宣教をすることなのです。それは、種蒔きの場所を選ぶのではなく、全ての土地に種を蒔きなさいというイエスの譬え話からもわかります。全ての人々に出ていくことが大切です。
とにかく恵みを取り出して出ていくことが大切です。準備は大切ですが、準備を完璧にするために、与えられためぐみを教会内で腐らせるのなら意味がありません。私たちが出ていく時に、与えられた力が十分に発揮されます。なぜなら一切の権威を与えられたのはイエスであり、そのイエスが私たちを送っているからです。ヨシュアたちがヨルダン川を渡る時、どのように渡りましたか?信じて渡り始めた時、水が堰き止められ道ができたのです。道ができるのを待っていたら、いつまで経っても渡ることができません。与えられたものに感謝して、出ていくことから始めるのが宣教なのです。
3。洗礼を施す
次に「洗礼を施す」という手順ですが、ギリシャ語で「バプティーゾ」という単語が使われています。これは、洗うといった意味はなく、完全に沈めるという意味があります。つまり洗礼とは罪を洗い流して綺麗になるのではなく、水に沈めて自分を無にすることを意味します。そして、料理をする手順の中で「調理する」ことに最も時間がかかるように、宣教においても「洗礼を施す」ことに最も時間がかかります。しかし、忍耐を持って待つことで、美味しい料理を食べることができるように、自分を無にすることで、御言葉をしっかり味わうことができるようになります。
イエスは誰かに洗礼を施すことはしませんでしたが、受けることで、キリスト者としての模範を示しました。なぜ弟子作りに、洗礼の儀式が必要なのでしょうか?洗礼は救いの必要条件ではありませんが、キリストの弟子となる公的宣言です。イエスは洗礼を受けて、自分の人生を無にして、宣教を始めました。私たちは宣教を始めるにあたって、自らも洗礼を受け、相手にも洗礼を薦める必要があるのです。実際に洗礼の儀式を受けたかどうかは別として、キリストの人生を歩む全ての者が通るべき、自分を無にする儀式が洗礼なのです。
無理矢理に行う結婚式に意味がないように、無理矢理に行う洗礼も意味がありません。しかし、片方が望む結婚式をもう片方が叶えることには意味があるように、イエスの教えに従って洗礼を受けることには大きな意味があります。洗礼は教えに従うための入り口なのです。洗礼を受けさせようとすると、様々な邪魔が入ります。しかし、重要なのは、良いことが起こって洗礼を受けるようになることではなく、悪いことが起こっても、自分を無にして洗礼を受けるようになることです。焦らすことなく、相手がイエスキリストを受け入れた時には、洗礼を薦めるようにしましょう。
4。教える
最後に「教える」という工程ですが、ギリシャ語で「ディダースコ」という単語が使われています。これは、単なる知識の伝達ではなく、相手が理解し従うように導くという意味があります。料理では見た目で美味しさが変わるため、器や盛り付け方で美味しく見せることも重要です。宣教での「教える」は、料理での「盛り付ける」に当たります。ただ与えるのではなく、教え通りに生きる私たちを見せることで、相手を正しく導くことができるのです。秋のバザーなど教会の行事で奉仕するのは、単に人手不足だからではありません。百聞は一見にしかずというように、奉仕する私たちの姿を人々に見せることで神の愛を伝えるためなのです。
イエスは弟子たちと寝食を共にしながら行動しました。なぜでしょうか?単に口で言って終わるのではなく、聞かせて、見せて、させてみて、体験させるためです。上からものを教えるのではなく、共にいることで教えるのがイエスの教育方針でした。私たちも人々を教える時、単なる講義で終わるのではなく、相手が理解しやすいように信仰を見せる必要があるのです。ただし、注意したいのは、宣教の目的は、あくまでキリストの弟子を作るためだということです。立派な人物になったり、祝福を受けて豊かになるためではありません。まして、教会に来る信者数を増やすためでも、自分の弟子を作るためでもありません。自分の信仰を見せる必要はあっても、見せびらかす必要はないのです。
最後に、弟子を作るのは私たちの力ではなく、聖霊の働きによるという事実を忘れないようにしましょう。私たちの人間の能力や努力で、弟子が出来上がるわけではありません。弟子になるかどうかは、聖霊の導きと、相手の自由意志を用いた応答によります。料理も同じです。私たちは心を込めて料理しますが、最終的に食べるかどうかは相手の自由に委ねられています。だからこそ、私たちに問われるのは「結果」ではなく、どれだけ忠実に出て行き、洗礼を授けようとし、教えようとしたか、その「行動」にあります。だから、私たちは最初の一歩を踏み出し、聖霊の働きに期待しながら忠実に従っていくことが大切なのです。
5。結論
宣教はキリストの弟子を作ることです。そのための3つの手順をイエスは教えています。まず「出る」こと。教会は恵みの保管庫ではなくパイプです。受けた恵みを眠ったままにせず、どんどん出していきましょう。そして、「洗礼を施す」こと。切ったり、調味料を加えたり、火を通したりして時間をかけることで、美味しい料理できます。同じように洗礼を受けさせる事には忍耐が必要ですが、教えに従うことのできる下地が整います。最後に「教える」こと。ただし、視覚情報によっておいしさが変わるように、ただ口で言って教えるのではなく、イエスのようにやって見せて教えることが重要です。キリスト者の姿を見せることで、本当のキリストの弟子を作っていくことができるのです。
私たち大阪中央教会は、時が良くても悪くても宣教を続ける教会です。それは宣教が教会にとってなくてはならないものだからです。そして教会に人を集めることではなく、キリストの弟子を作ることが宣教だと考えています。そのため私たちは、恵みを貯め込むのではなく溢れさせ、自分を表すのではなく無にする事を目指し、言葉だけで終わるのではなく、行動で人々にキリストを示す教会を作っていきましょう。


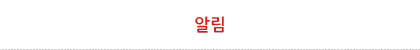
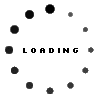
댓글0개