20241229 日曜午後礼拝
聖書:ナホム1:2
題目:慰めのある復讐
内容:人間の復讐は、一時的な自己満足しか得られず、その代償は悪として裁かれることです。なぜなら人間は罪のため、公平に裁くことができないからです。相手は悔い改めるどころか、同じように復讐を考えるでしょう。一方で神様の復讐は、公平であり、不公平によって苦しむ私たちを慰めてくれます。また、私たちは復讐ではなく、善を行うことで、相手に自身の悪を気付かせ、慰めを得させます。
説教者:高曜翰 副牧師
1。不公平な裁き
有名なもので1894年のフランスで起きたドレフュス事件というものがあります。フランスの諜報部が送り込んだスパイが、ドイツ大使館で機密メモを入手しました。しかしその筆跡はフランス陸軍の誰かが書いたと思われるものでした。ドイツ軍に情報を流している犯人を探すことになりましたが、フランス陸軍で唯一のユダヤ人であるドレフュス大尉に嫌疑がかかりました。杜撰な筆跡鑑定で一方的にドレフュスを犯人として断定し、反逆罪で逮捕し、無期流刑の判決を出しました。ドレフュスは群衆の前で、軍バッジを剥ぎ取られ、軍刀をへし折られました。新聞も「ユダヤ人の売国奴、逮捕される」と報道し、誰もこの不当な判決を疑いませんでした。カトリック教会における根強い反ユダヤ主義による差別が原因と言われています。ドレフュスの妻と弟は、弁護士や政治家、新聞紙に訴えましたが、なかなか聞く耳を持ってもらえませんでした。
そんな中でも、この判決に異議を申し立てる人々がいました。新しい参謀本部情報部長のピカール中佐です。独自の調査の結果、エステラージー少佐が真犯人だと特定しました。また、作家のエミールゾラが軍部を批判しました。しかし、陸軍は、軍事裁判の権威を守るため、ピカールの申し出を却下し、エミールゾラを侮辱罪で訴えました。エミールゾラは身を守るためロンドンに亡命してしまいました。残念なことに、真犯人のエステラージーは裁判で無罪判決を受け、その後国外逃亡しました。また、ドレフュスの弁護士は銃撃事件に遭い、負傷してしまいました。そんな中、ドレフュスは大統領特赦で出獄することになりましたが、それはドレフュスが無罪ではなく、有罪であることを意味するものに変わりありませんでした。出獄してもドレフュスは「名誉なき解放など何の意味もない」と言い、自分が無実であることを伝え続けました。1906年、事件から12年後にようやく無実であることが認められました。ドレフュスはいつ大きな慰めを受けたでしょうか?出獄した時ではありません。公平な裁きが行われ、無実だと認められ時です。彼が求めていたのは正しい裁きです。
いじめていた子供は時間が経てば忘れますが、いじめられていた子供はいつまでも忘れません。靴で踏んだ側は覚えていないが、踏まれた側は覚えているのと同じ理屈です。いじめられた子供は、一体いつ慰められ、苦しみから解放されるでしょうか?いじめがなくなった時ではありません。いじめていた子供が、公平な裁きを受け、自分の罪に気付き、悔い改める時です。それは国単位でも同じです。侵略した側が忘れても、侵略された側はいつまでも覚えています。そして慰めを受けるのは、侵略した側が公平な裁きを受け、自分の罪を真に認めた時です。いじめられていた子供にも問題があるというのは、いじめる側の、力が正義と考える人々の一方的な理論に過ぎません。確かに防衛力を持つ必要性はありますが、弱者が悪いと考えるのは、ただの論理のすり替えです。公平な裁きにより、いじめっ子が自分の罪を認識する時、本当の慰めが生まれるのです。
2。ニネベへの裁き
ナホム書はエルコシ出身のナホムによって記されました。エルコシの場所は北ガリラヤなどと言われますが、はっきりとはわかっていません。内容から考えるとテーベ陥落の前663年からニネベ陥落の前612年の間だと言われています。ここで大切なのは、この本がアッシリアに苦しめられているイスラエルの民に向けて書かれたということです。単に神様に逆らうものはアッシリアのように滅びますよ、ということだけを伝えたいのではなく、神の公平な裁きによってイスラエルを慰めることが目的となっています。
アッシリアは1400年の歴史を誇る、オリエント初の統一帝国です。鉄製の戦車と騎兵隊で強大な国家となりましたが、政治面においても後のペルシャやローマのモデルとなるほど優秀でした。ただ、1番の問題は残虐さで人々を支配したということです。重税を課し、そのために反乱をした人々を、串刺しにし、皮を剥ぎ、目をくり抜き、切断した頭を飾って食事をするなどの行為を行いました。こんなひどいことをしながらも、その王たちは自らを「正義の王」と称したのです。ニネベはアッシリアの首都であり偽りの正義の象徴でした。
それにも関わらず、神様は預言者イザヤを通して「アッシリアは我が作品」と言いました。そしてアッシリアの人々を救うために、神様は預言者ヨナをニネベに遣わしました。アッシリアは神の民である北イスラエルを滅ぼし、南ユダをも幾度と攻撃し、領土を奪い、属国にした国なのにです。神様はそんなアッシリアの人々が救われることを望んでいたのです。ヨナを通して、一時的に神の裁きを免れたニネベですが、残念ながら完全に悔い改めることはできませんでした。その結果、神様はニネベの審判を決定し、ナホムを通して人々に伝えたのです。神様は怒るに遅い方ではありますが、罪を見過ごす方ではありません。
神様はニネベに対して「あなたはテーベに優っているか?」(ナホム3:8)と尋ねました。テーベとはギリシャ名であり、本来はノ・アモンと言います。アモン神の都という意味です。エジプトの首都となり、人口75,000ほどに膨れ上がった、世界最大の古代都市でした。当時はエジプト人ではなく、エチオピア人の王朝で、プト人、リビア人と同盟を組み強固な国を形成していました。その中でもテーベはナイル川の恩恵を受け、運河によって囲まれ、難攻不落の城塞都市として有名になっていました。ホメロスは大袈裟に「100ある城門から200の兵が戦車を連ねて出撃できる」と歌っています。しかし、「乳飲子は投げ捨てられ、貴族はくじ引きにされ、有力者たちは鎖に繋がれた」(ナホム3:10)とあるように、アッシリアによって残虐に滅ぼされてしまいました。
一方で、その後、ニネベは人口10万以上の世界最大の都市となり、長さ13km、基礎部分からの高さが20mになる城壁に囲まれる城塞都市として君臨するようになりました。チグリス川の恩恵を受け、18本の運河による精巧な給水システムを作り、戦車などの軍備や道路の改善を続け、万全の準備をしていました。そのおかげでニネベで戦争が始まった当初は何とか持ち堪えていましたが、チグリス川の反乱により、水路からのメディア・バビロンの連合軍の侵入を許してしまい、陥落しました。その後、前609年にはエジプトの援軍も虚しく、アッシリアという国は地上から完全に消え去ってしまいました。
ナホム書を通して、神様が私たちに見せているものは何でしょうか?それは今日の本文に凝縮されています。まず、「妬む神」という言葉ですが、これは契約用語です。通常、妬みとは悪い意味ですが、ここでは正しい意味です。結婚したのに浮気したら妬むという意味と同じです。そして「復讐する神」という言葉ですが、気まぐれではなく、罪を決して放っておかないという意味です。通常、復讐とは悪い意味ですが、公平な神様だけに許された行いです。また、「憤る神」という言葉ですが、人間のように、自制心を失った怒りや自分勝手な怒りではなく、公平に基づいた正しい怒りです。義憤という意味です。これらはパートナーであるイスラエルを苦しめたアッシリアに対する神様の思いです。確かにイスラエルは神様を裏切って浮気をしましたが、そのイスラエルに大きな苦しみを与えたニネベを裁くことで、イスラエルを慰めることができるのです。テーベを引き合いに出したのは、同じ報いを受けることをを教えるためです。力を誇り、力で生きる者は、力で滅びるということです。アッシリアの完全なる滅亡は、単にイスラエルのうさを晴らすためではなく、公平な裁きが行われることで、イスラエルが慰められるためなのです。
3。復讐による慰めを受けるには?
第一に、復讐は神様だけができるということを忘れてはいけません。パウロは「愛する者たちよ。自分で復讐をしないで、むしろ、神の怒りに任せなさい。なぜなら、『主が言われる。復讐はわたしのすることである。わたし自身が報復する』と書いてあるからである」(ローマ12:19)と言いました。なぜ人が復讐してはいけないのでしょうか?「目には目を、歯には歯を」という律法が、やりすぎてしまう人間性を教えています。人の復讐では、公平さがなくなり、復讐が復讐の連鎖を生み、罪となるからです。イエスは不当な逮捕、不当な裁判、不当な刑罰を受けましたが、反論はしても復讐はしませんでした。地上における唯一の義人でしたが、自分で復讐するのではなく神様の復讐に任せました。パウロは「義人はいない、一人も居ない」(ローマ3:10)と言いました。そうです。私たち神の民が望むべきは自分の満足感ではなく、公平な裁きです。だから復讐は公平な神様にしか任せられないのです。
第二に、私たち人間は、復讐の代わりに善を行うことで慰められることができます。パウロは「むしろ、「もしあなたの敵が飢えるなら、彼に食わせ、かわくなら、彼に飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃えさかる炭火を積むことになるのである」(ローマ12:20)と言いました。なぜ敵に良いことをしてあげないといけないのでしょうか?復讐しても相手に芽生えるのは復讐の心だけだからです。盗みを働いたせいで、警察に銃で撃たれ、捕まった強盗は、果たして自分の罪を悔い改めるでしょうか?いいえ。強盗は銃で撃った警察官を悪いと訴え、悔い改めることはしないでしょう。聖書は、善を行うことで、相手の良心を責め、悔い改めに導くことを教えています。「燃える炭火を積む」とは、昔エジプトであった習慣です。自分の罪を悔い改めた者が、「燃える炭火」を乗せて町中を歩くというものです。私たちが善を行うことで、敵を悔い改めに導くことができるのです。イエスは十字架の上で、「父よ、彼らをお許しください。自分では何をしているの分からないのです」(ルカ23:34)と、とりなしの祈りをしました。悪に対して善を返すなら、相手はいつか、自らの悪を恥じます。相手が自分の罪に気付き、悔い改めることで、私たちは本当の慰めを得ることができるのです。
だから私たちは悪に対して善を行って勝利を得ましょう。パウロは「悪に負けてはいけない。かえって、善をもって悪に勝ちなさい」(ローマ12:21)と教えています。嫉妬、復讐、憤りで報いることは、私たちを相手と同じ悪人にするだけです。悪の連鎖はエスカレートしていき、私たちを残虐なアッシリアのようにさせます。1400年続いたアッシリアが完全に消滅したのは、その悪が行きすぎたためです。復讐の先にあるのは、神の裁きです。恩を仇で返すのがこの世の常なので、なかなか思い通りにはいきませんが、悪に悪をもって報いるのではなく、善をもって報いる復讐こそが、私たちに与えられた最良の方法なのです。
4。まとめ
復讐による慰めとは何でしょうか?それは神様が行う公平な裁きであり、私たちはその公平な裁きによって慰めを得ることができます。人の復讐は不公平であるため、完全な慰めを得ることはできません。そして、人ができる復讐方法とは、善をもって悪に報いることです。善を行うことで、相手に自らの罪を自覚させ、悔い改めに導き、私たちは慰めを得ることができます。私たちを慰めてくださる神様を信じて、悪を行わず、善を行うことで勝利を得ましょう。


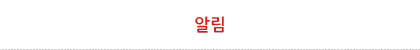
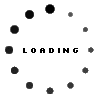
댓글0개