20250629日曜午前礼拝
聖書:ルカ3:7−14
題目:分け与える実り
讃美:88、255、257
説教者:高曜翰 牧師
“さて、ヨハネは、彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆にむかって言った、「まむしの子らよ、迫ってきている神の怒りから、のがれられると、おまえたちにだれが教えたのか。 だから、悔改めにふさわしい実を結べ。自分たちの父にはアブラハムがあるなどと、心の中で思ってもみるな。おまえたちに言っておく。神はこれらの石ころからでも、アブラハムの子を起すことができるのだ。 斧がすでに木の根もとに置かれている。だから、良い実を結ばない木はことごとく切られて、火の中に投げ込まれるのだ」。 そこで群衆が彼に、「それでは、わたしたちは何をすればよいのですか」と尋ねた。 彼は答えて言った、「下着を二枚もっている者は、持たない者に分けてやりなさい。食物を持っている者も同様にしなさい」。 取税人もバプテスマを受けにきて、彼に言った、「先生、わたしたちは何をすればよいのですか」。 彼らに言った、「きまっているもの以上に取り立ててはいけない」。 兵卒たちもたずねて言った、「では、わたしたちは何をすればよいのですか」。彼は言った、「人をおどかしたり、だまし取ったりしてはいけない。自分の給与で満足していなさい」。”
ルカによる福音書 3:7-14 口語訳
1。信仰のあるなしはどこで決まる?
私たちが「信仰」と聞いて思い浮かべるものは、祈ること、教会に通うこと、聖書を読むことなど、ある意味で“宗教的”な行為が多いのではないでしょうか。しかし、今日の聖書箇所に登場するバプテスマのヨハネは、そのような宗教的行為を第一に評価していません。むしろ彼は、悔い改めたという信仰告白が、現実の社会生活や経済活動にどう現れるか、という点を厳しく問いかけています。
2。なぜ怒られた?
バプテスマのヨハネは洗礼を受けに来た人々を褒めるのではなく、「まむしの子らよ」と叱りました。原文では「毒蛇」を指し、「蛇」はサタンなど偽善的な悪者を象徴しています。つまり、「まむしの子ら」というのは、毒と偽善を合わせ持つ者を表しています。言い換えると、神を恐れているように見せかけて実は神を侮っている人々を指しているのです。
なぜヨハネはこれほど強く批判したのでしょうか。それは、洗礼を受けに来た人々の中に、形だけで神の怒りを逃れようとする者たちがいたからです。マタイによる福音書によると、それは特にサドカイ派やパリサイ派の宗教指導者たちであることがわかります。彼らは「アブラハムが私たちの父だ」と血統に安心し、外面的な信仰行為(洗礼)で救われると思っていたのです。ヨハネは彼らの上辺だけの心を見抜いて叱ったのです。
「石ころからでもアブラハムの子孫を作ることができる」と語ったのは、ユダヤ人の民族的誇りを打ち砕き、神の主権によってのみ物事が決定されることを教えるためです。「斧はすでに木の根元に置かれている」というのは単なる警告ではなく、すでに神の審判が始まっているという意味です。そのため、ヨハネは「悔い改めにふさわしい実」を結ぶように迫っています。それは、頭だけで考えて終わるのではなく、行動によって示されるべきことなのです。
3。どうすればいい?
「それでは私たちは何をすれば良いか?」という問いに、ヨハネは「下着を二枚持っている者は、持たない者に分けてやりなさい。食物を持っている者も同様にしなさい」と答えました。ここで言う下着とは、現代のパンツやシャツのようなものではなく、当時の基本的な一枚物の衣類を指しています。貧しい人々はこの衣類一枚で生活していました。裕福な人はその下着の上に上着を着ていましたが、ある程度余裕のある人々はこの下着を二枚重ねて着ていました。気温差が激しい地域だったため、防寒着としての意味もありましたが、見栄や体裁を整えるために重ね着している場合もありました。この下着を持っていない者というのは、服がなくて外出もできない人々を意味します。つまり、ヨハネは生きるために必要な基本的な衣服を分け与えることが、神に喜ばれる正義であると語っているのです。
ルカは「群衆」という言葉を使って普遍化していますが、実際には宗教指導者たちに向けられた言葉と捉えられます。当時、サドカイ派は支配国ローマに良く見られようとし、パリサイ派は中流階級の支持を得ることに必死でした。共通しているのは、いずれも人からの賞賛を得るために、他人よりも多くのものを所有しようとしていた点です。しかしヨハネは、他人より多く持とうとするのではなく、むしろ分け与えることが正義であり、洗礼を受ける以上に重要であると語っているのです。
次に取税人たちが来て、「どうすれば良いか?」と尋ねました。ヨハネは「決められた以上に取り立ててはいけない」と答えます。取税人は人々に嫌われていた職業でした。なぜなら、支配者であるローマの代理人として、同胞からローマへの税を取り立てる存在だったからです。嫌われた取税人たちは、その悔しさから税を規定以上に取り立てていた場合もありました。一方ローマは、彼らの不正を黙認しました。同胞同士の憎しみや分断を利用することで、ローマへの反感が結集しないようにしていたのです。ヨハネの言いたいことは明確です。たとえ差別されている立場にあっても、それは不正を行う言い訳にはなりません。どんな職業においても、偽りではなく誠実であることが正しい道であり、洗礼を受ける以上に大切なことなのです。
さらに兵士たちも来て、「どうすれば良いか?」と尋ねます。ヨハネは「人を脅したり、だまし取ったりしてはならない。自分の給料で満足しなさい」と語ります。ヨハネがヨルダン川沿いのペレア地方で活動していたことを考えると、これらの兵士たちはヘロデ・アンティパスの兵士だったと考えられます。そしてその場にいたということは、取税人の護衛として共に行動していた兵士だった可能性があります。兵士たちは給料の安さから、自分たちの持っている力を使って、ちk貧しい民から恐喝や賄賂などで不正に金銭を巻き上げていました。どんな環境であれ、職権濫用は罪であり、欲望や誘惑に屈することは不正義です。ヨハネは、安い給料も言い訳にはならないとし、どのような職業でも正義を行うことが重要だと語っています。
洗礼とは、水で罪の汚れを落とす儀式ではありません。水に入ることで過去の自分を終わらせ、キリストの人生を生きる新しい自分に生まれ変わることを意味します。洗礼とは、罪を清めるというよりも、キリストの生き方を自らのものとする信仰告白なのです。そしてその信仰には、真の悔い改めが伴います。悔い改めとは、自分を清め高めることではなく、人々に分け与える具体的な行動を生み出すことです。
4。適用
第一に、悔い改めた人とは、得ることではなく、与えることを目的とする人です。
“わたしは、あなたがたもこのように働いて、弱い者を助けなければならないこと、また『受けるよりは与える方が、さいわいである』と言われた主イエスの言葉を記憶しているべきことを、万事について教え示したのである」。”
使徒行伝 20:35 口語訳
私たちは日々の生活の中で、どれだけ「持っていること」に安心を置いているでしょうか。しかしヨハネは、所有することではなく、分け与えることにこそ神の喜ばれる実があると語ります。そしてイエスも「受けるより、与えるのが幸いであると」言っています。平安を得られる悔い改めとは、所有を手放し、必要とする人のために与える行動へと変わることなのです。
第二に、悔い改めた人とは、損得勘定ではなく、誠実さを大切にする人です。
“あなたは施しをする場合、右の手のしていることを左の手に知らせるな。 それは、あなたのする施しが隠れているためである。すると、隠れた事を見ておられるあなたの父は、報いてくださるであろう。”
マタイによる福音書 6:3-4 口語訳
取税人が尋ねたように、職業生活の中でどのように正義を行うかが問われています。誰も見ていないときでも、神は私たちの誠実さをご覧になります。イエスは、隠れて善行を行うことを勧めています。人に見られて評価されることを期待すると、誠実な行いができないからです。損か得かではなく、正しいことをする。それが悔い改めた者の歩みです。
第三に、悔い改めた人とは、自分の力を自分のためではなく、人のために使う人です。
“あなたがたの間でかしらになりたいと思う者は、すべての人の僕とならねばならない。”
マルコによる福音書 10:44 口語訳
権力や影響力を持つ立場にいると、それを自分の利益のために使いたくなる誘惑があります。しかしヨハネはそれを戒め、「満足すること」、すなわち他者に危害を加えず、節度をもって生きることを勧めます。イエスも、人に仕えられるのではなく、人に仕えるように教えています。私たちが持っているものは、仕えられるためではなく、仕えるために与えられたのです。悔い改めとは、持っているものを他者のために用いる生き方へと変えられることなのです。
5。まとめ
悔い改めの実は、決して漠然としたものではありません。それは、「与えること」「誠実であること」「力を人のために使うこと」といった具体的な行動によって示されます。神の前に立つとき、私たちは自らの信仰をどのように証明できるでしょうか。洗礼や宗教的な儀式を受けたということではなく、日々の生活の中でどれほど「神の愛と正義」を実践してきたかが問われるのです。
今日、私たち一人ひとりに与えられている問いは、「それでは私たちは、何をすれば良いのでしょうか?」という群衆の問いです。そしてその答えは、「あなたが持っているものを、必要としている人に分け与えなさい」というシンプルで力強い呼びかけです。今週、誰かに何かを分け与えることから、あなたの信仰を実践してみませんか?


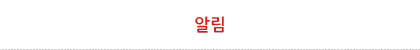
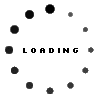
댓글0개